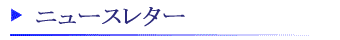
JIIA研究テロ戦争と国際秩序
森本 敏
冷戦後十年を経て、国際社会は依然として新秩序を模索しているが、まだ、結論は出ていない。
しかし、今回米国に発生した同時多発テロとそれに対する対応措置を通じて新たな秩序に向けた方向が見え始めてきたように思われる。
いうまでもなく、冷戦期の世界秩序はイデオロギーに基づく東西対立構造によってできあがっていた。冷戦期における脅威はしたがって、東西間に起こる核戦争であり、全面戦争の恐怖であった。
冷戦の終焉以来、新秩序を説明する論理が模索され、ハンティントンの文明の衝突論が注目されたものの、いまだ冷戦後の秩序を説明する論理とはなっていない。
他方、冷戦後の脅威・危険は冷戦期とは異なり、地域紛争、大量破壊兵器拡散、テロ・国際犯罪、麻薬、経済格差、人口増加に伴う諸問題など広範に及んでいる。そして、国際社会はこうした冷戦後における深刻な脅威・危険などに対してやむをえず武力介入を行って問題を解決してきた。国連が設置された時には予想しなかった事態である。
テロは従来、犯罪として扱われていたのであり、警察活動によって対応すべき問題である。それが今回はそうならなかった。その最大の理由は今般のテロが従来のテロという概念をはるかに越えた重大かつ、深刻な事態を招き、また、警察ではなく軍事力によって対処しなければならないような対象であったためである。そもそも国際法上、テロについて明確な定義はない。しかし、米国で9月11日に発生した同時多発テロ事件は米国の国家社会システムを根本的に崩壊させるものであり、米国はこのテロ事件を「新しい戦争」の始まりと概念している。新しい戦争とは、戦争の主体が従来の概念である主権国家ではなく、テロのような集団やネットワークなど国境を超えた性格をもっているという特徴をもつ。
さらに、この主体が通常であれば軍備や兵器システムなどの武力を行使するのが通常であるが、今回の事件で明らかなごとく民間航空機をハイジャックして多数の無垢な民間人を人質にして、これを凶器にして国家・社会のシステムを崩壊させようとしたのであり、その手段は日常生活的な意味合いをもつ。その点で、この戦争は宣戦布告などが行われず、探知、早期発見が困難である。また、通常、戦争であれば戦争を行う主体が民族の独立や主権の確保、領土の拡張・確定といった明確な目標を獲得するものであるが、今回のテロ事件にみられるように、そのような目標を獲得したかどうかも不透明である。そのため紛争解決や紛争予防が困難をきわめる。したがって、この戦争は開戦も終戦も不明確なのである。
さらにいえば、武力行使が行われる戦場というものがなくなっていることも特徴である。例えば、このテロ事件に次いで米国内に広がった炭そ菌事件が引き起こした米国内の混乱と動揺を見ても明かなごとく、新しい戦争は日常生活の中に入りこんでおり、通常の戦争で見られるような戦場すらない。
こうしたいくつかの特徴をもつ新しい戦争には国家および国民が軍隊と国家機関の総力を挙げて立ち向かわなければならなくなっている。この戦争は文化・文明の発達している社会ほど脆弱な体質をさらすという性格も有しており、その点で、この戦争は国家発展の非対称性が大きいほど、発展途上国に有利になるという特徴もある。
今回、米国は米国に対する明白な攻撃に対応するため国連憲章によって認められた個別的自衛権を行使して対処しようとしている。本来、自衛権は急迫不正の侵害が行われた場合、これに対してやむを得ざる措置を、国連安保理が必要な措置をとってくれるまでの間に行使できる権利として主権国家に認められているものであるが、米国は今回のテロ事件を引き起こした実行犯の背後にいる組織やその他のテロ集団が健在であるかぎり、いつでも米国に対する同様のテロ事件が行われる危険性が存在しており、これを排除することは自衛権の範囲であるという考えである。
このことは今回、米国が第一期作戦としてアルカイダおよびこれと共闘関係にあるタリバン政権を物理的に破壊させえたとしてもビンラーディンの指揮する国際テロ集団が世界的に分散し、これを支援する諸国家がこのようなテロ集団を保護し、訓練施設を供与し、資金を提供しているかぎり、国際的なテロ活動が根絶できるとは考えておらず、したがって第一期が終了した後の成果、米国内の世論や国際情勢の動きを考えつつテロ支援国家に戦域を拡大することも自衛権行使と考えている可能性がある。いずれにせよ、第一期作戦はアフガニスタン内にいるタリバン、アルカイダおよびビンラーディン個人を対象としたものであるが、それは作戦目的を明確にし戦域を限定することによって成果を確実なものにするための手段に過ぎない。
米国内ではこのように作戦の目的と範囲を明確に限定して、作戦の成果を確実に達成すべきであるというパウエル国務長官の立場が採用されたが、米国には米軍の全戦力を駆使して戦域を拡大し、国際テロとの長期にわたる忍耐強い作戦にとりかかるべきとの意見がある。この限定作戦と戦域拡大作戦は結局、どちらかが選択されたのではなく、まず、第一期作戦として限定作戦にとりかかり、その後の事態を勘案して第2期作戦としての戦域拡大作戦に移行するという決定が行われたのであり、まず、第一期作戦を成功させてから、次の段階を検討するということであろう。
もっとも深刻な問題は地上戦に突入後にあまりに時間がかかって、当初目標を達成できないという事態が生じ、この間に民間人の死傷者のみならず、米兵にも死傷者が多数でて、イスラム社会の反発が高まり、それにつれて国際世論や米国内世論の支持が低下するという懸念である。米国は今回の軍事力行使にあたり、今までになく各種の外交努力を行ってきた。米国が国際世論をここまで気にしながら外交努力を続けてきたのはこの作戦の困難さを示すものである。
さて、こうした米国のテロ対応作戦が終了した後、今回の一連の軍事作戦が国際秩序にいかなる意味合いをもつであろうか。
第一は米国が一極主義の国際社会においてそのリーダーシップを強化できるかどうかである。米国は今回、国連安保理に頼らず、同盟諸国を軸にした同盟協力によって問題解決をしようとしている。これに多くの国が同調し、国際協調がはかられロシアや中国までも米国を中心としたテロ撲滅のための国際協力を支持している。米国はもはや孤立主義には戻れない。米国が内向きになりたいと国民が思っても米国の国際的リーダーシップが強化される可能性がある。しかし、このような状況になる前提は少なくとも米国が第一期作戦に成功し、その目標を達成することである。他方、そうではなく、米国が第一期作戦に失敗すれば米国はきわめて内向きな社会に回帰していくだろう。したがって、第一期作戦の成否は国際秩序の行方に重大な影響を与える。
第二は今回のテロをめぐる一連の活動は、宗教戦争ではないと米国は主張している。米国を中心とするテロ対応措置の根底にある意識は米国が進めてきた価値観への同調である。すなわち、このことを推し進めて考えれば、米国の価値観を共有しうる諸国家のグループとこうした価値観を共有できないグループとにわかれた国際秩序を形成する可能性がある。これは必ずしも、イスラム対反イスラムではないが、冷戦後10年にして初めて国際秩序構築の新たな要因が浮かび上がってきたといえるであろう。
(拓殖大学国際開発学部教授)



© Copyright 2001 by the Japan Institute of International Affairs
|

