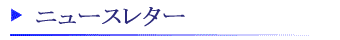
JIIA研究同時多発テロ事件とパレスチナ問題
The Terrorist Attacks and the Palestinian Problem
立山良司
TATEYAMA Ryoji
- <JIIAにおける研究活動>
- 「米国と中東」研究会・主査(1997年)
- 「米国の対外政策と中東」研究会・主査(1998年)
- 「イスラエル内政に関する多角的研究」研究会・主査(2001年)
- <専門分野>
- 中東現代政治・国際関係
- <略歴>
- 防衛大学校総合安全保障研究科兼国際関係学科教授。1947年東京都生まれ。1971年早稲田大学政治経済学部政治学科卒。(財)中東調査会研究員、在イスラエル日本大使館専門調査員、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)アンマン本部総務課長、(財)中東経済研究所研究主幹などを経て、1997年4月より現職。
- <主要著書>
- 『イスラエルとパレスチナ』(中公新書)1989年
- 『中東新時代のパラダイム』(TBSブリタニカ、共訳)1992年
- 『エルサレム』(新潮選書)1993年
- 『中東和平の行方:続イスラエルとパレスチナ』(中公新書)1995年
- 『中東』(自由国民社、編著)第2版1998年
- 『揺れるユダヤ人国家:ポスト・シオニズム』(文春新書)2000年

米国での同時多発テロ事件を契機に、パレスチナ問題が改めて関心を集めている。ブッシュ米大統領は11月の国連総会での演説で、テロ撲滅のための国際的な取り組みの必要性を訴えるとともに、パレスチナ国家の樹立を前提としたパレスチナ問題の解決を呼びかけた。
本年度、われわれは国際問題研究所の研究プロジェクト「イスラエル内政に関する多角的研究」に携わっている。研究内容はイスラエルの政党政治や軍事戦略といった内部からの視点に加え、アラブ諸国やイスラーム主義から見た「イスラエル問題」、さらに中東和平プロセスとの関連といった多様な問題関心からなっており、まさに「多角的な研究」だ。この研究プロジェクトの進行中に、同時多発テロ事件が発生した。当然、研究会でも事件やその後の展開を視野に入れた議論を行っている。
もちろん、パレスチナ問題やアラブ・イスラエル紛争が国際テロの直接的な原因ではない。むしろ、パレスチナ人の指導者の一人で、アラブ連盟の広報担当を務めているハナン・アシュラウィー女史が「彼らは自分たちを正当化するためパレスチナ問題をハイジャックしている」とウサマ・ビンラーディン氏らを非難したように、パレスチナ人の側には自分たちの問題が他の紛争や対立の口実に使われることへの強い反発がある。
その一方で、パレスチナ問題へのより公正な取り組みがテロを産む土壌を少しでも減らすことは事実だ。1998年にケニアとタンザニアの米国大使館が自爆テロの標的となった時、父親のブッシュ政権のCIA長官だったロバート・ゲイツ氏は、テロを減らす一つの有効な対策として米国はイスラエルに対しもっと厳しい姿勢を取るべきだと指摘している。
1993年にオスロ合意(「暫定自治に関する諸原則の宣言」)が調印された時、世界は20世紀中にパレスチナ問題が解決するのではないかとの期待を持った。だが、その期待は実現しないどころか、イスラエルとパレスチナ人の対立はいっそう激化してしまった。オスロ合意以降の和平プロセスはなぜ、停滞し、崩壊に近い状況にまで追いこまれたのだろうか。
一つの大きな要因は、治安や安全の問題に関するイスラエルとパレスチナ人のパーセプションの違いだ。イスラエルのユダヤ人が「平和」に求めているのは「安全」だ。それは三つのレベルからなっている。大量破壊兵器による攻撃からの安全、周辺アラブ諸国との通常兵器による戦争からの安全、そうして日常生活レベルでの安全である。最後の日常生活レベルでの安全は、パレスチナ人との関係に直接結びついている。安心してバスに乗れる、心配なく子供たちを学校に送り出せる、といった身近なレベルで安全が確保されていることだ。それだけにイスラエル国民にとって大変重要な問題だ。
一方、「平和」によって実現されるべきパレスチナ人の「安全」とは、軍事占領や外部勢力による支配や侵略からの解放であり、自分たちの土地を奪われないという保障だ。こうした安全を確保するためにはイスラエル軍が占領地から撤退するだけでなく、主権を持った独立国の樹立と、その独立を担保する国際的な保障が不可欠となる。パレスチナ人はイスラエル建国によって英委任統治領パレスチナの約75%に当たる土地を失い、多くが難民となった。さらに残りの25%に当たる東エルサレムやヨルダン川西岸、ガザ地区も30年以上にわたり占領下に置かれ、ユダヤ人による入植活動で土地を奪われてきた。そのためパレスチナ人にとって、安全とは自分たちの民族としての存在を確保する絶対的な要件だ。
現在の和平プロセスは「土地と平和との交換(land for peace)」原則に基づいている。この原則は、イスラエルが占領地から撤退する一方、アラブ側はイスラエルの存在とその安全を認めるとの表現で、1967年の第3次中東戦争後に成立した国連安保理決議242に盛り込まれている。この原則はこれまでにエジプト・イスラエル間で履行され、シナイ半島の全面返還が両国の関係正常化の前提となった。
オスロ合意もこの「土地と平和との交換」原則に立脚している。問題は双方にとって「平和」の裏づけとなる「安全」の意味が違うことだ。イスラエル側は安全が確保されないかぎり、つまりパレスチナ人による「テロ」が収まらないかぎり、占領地を返還しようとしない。「土地と平和との交換」というよりは「土地と安全との交換(land for security)」といわれる所以だ。
一方パレスチナ人は、イスラエルが占領地から全面撤退しパレスチナ独立国家が樹立されるまで「安全」は確保されておらず、そのための「武力解放闘争」は正当な行為と考えている。現在、パレスチナ自治区となっている地域は西岸では41%に過ぎず、「独立」にはほど遠い。
オスロ合意を含め、イスラエルとパレスチナ間のさまざまな合意には治安・安全保障問題への取り組みがかなり盛り込まれている。暫定自治を実際に開始するためのガザ・エリコ合意(1994年5月)は付属議定書で、治安維持に関するさまざまな措置や協力体制を詳細に規定している。ヘブロン合意(1997年1月)やワイ合意(1998年10月)には、テロ防止のため米国の積極的な役割が盛り込まれている。
こうした試みはイスラエル・パレスチナ間に効果的な安全保障レジームを樹立するための努力といってよい。ロバート・ジャービスによれば、安全保障レジームとは「諸国家が他国もまた相互主義的な行動を取るであろうとの確信に基づき、自らの行動を制限することを容認するような原則、規則、および規範」で、「短期的な自己利益を追求することに留まらない協力形態」とされている。
アラブ・イスラエル紛争で安全保障レジームが効果的な役割を果した例は、シナイ半島におけるエジプト・イスラエル間の各種の安全保障措置や、イスラエル・シリア間のゴラン高原での国連平和維持活動に関係したレジームがある。この二つのケースはいずれも国家と国家との関係での安全保障レジームだ。そこでは国家が行使する「暴力」の意味付けにも一定の共通性があり、それゆえ、レジーム構築に向かった段階で、当事者は原則や規則、規範をある程度共有していた。
一方、イスラエルは国家だが、パレスチナ側は非国家、というよりは国家になろうとしている前国家的な存在だ。それゆえ、「暴力」の意味付けも「安全」の内容も大きく異なっている。こうした非対称の状況においては、相互主義を期待できるような原則や規則、規範が共有されているとはいい難い。その結果、安全保障レジームを構築しようとする取り組みにもかかわらず、効果的なレジームを生み出すことはできなかったのである。
こう考えるならば現在、行き詰まり状態になっているイスラエル・パレスチナ間の和平プロセスに突破口を開く道は明らかだろう。国連の場などを用い、国際社会がパレスチナ国家の樹立の道をもっと積極的に切り開くことだ。ブッシュ大統領の国連演説に見られるように、同時多発テロ事件以降、パレスチナ国家樹立の必要性が改めて指摘されている。それはパレスチナ人の自決権を回復するという最低限の要求を満たすだけでなく、暴力の連鎖に終止符を打つための効果的な安全保障レジームを作るという視点からも、推進されるべき議論である。
(防衛大学校国際関係学科教授)



© Copyright 2001 by the Japan Institute of International Affairs
|

