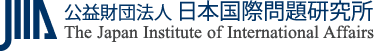CSCAP−CSBM国際ワーキンググループ第13回会合報告 (赤倉 慶太)
表記会合が、5月22日〜24日にわたり、ワシントンDCで開催された。今回のワークショップは、アジア太平洋地域の多国間信頼醸成のための政策提言を目的とする国際作業部会と、核エネルギー情報公開のための具体的なプロジェクトを推進している原子力専門家会合を合同で行ったものである。会合には、カナダ、中国、日本、ニュージーランド、北朝鮮、シンガポール、台湾、米国、国連から28名の参加があった。議事内容はこれまでの各プロジェクト(Trans-parency Website, Nuclear Energy Data Book)の進捗状況のレヴュー、各国使用済核燃料貯蔵計画と、中国軍事力の分析であり、Calvert Cliff原子力発電所の見学会も含まれた。 今回のワークショップは、筆者にとって2回目のCSCAP会合参加であった。 筆者は電力会社の社員であるが、原子力分野での勤務経験はなく、「原子力専門家」の肩書きで参加するのが少々心苦しく思いつつも毎回非常に貴重な経験をさせていただいている。前回のソウルは「原子力専門家」会合であったため、内容が電力・原子力の分野に集中しており、議事内容の理解にとくに苦労しなかったが、今回はむしろ核兵器・安全保障問題が中心であったため、知識の不足を痛感した。日本の電力会社の人間の頭では、原子力といえば経済と環境にしか結びつかないのだが、今回の参加者の間ではまず安全保障と結びついており、ここに問題意識の差を大きく感じた。 筆者が日本の核燃料サイクル計画に必要な中間貯蔵計画の説明をしたところ、米国の安全保障専門家から使用済み核燃料を用いた日本の核兵器の開発の可能性についての指摘を受け、大変当惑した。彼は3ヵ月あれば日本は核兵器を作れるといっていた。 確かに日本の技術で燃料用のウランを兵器用の高純度のものに精製することはできるかもしれないし、H2の失敗はあっても、核弾頭を搭載するミサイルの開発も純技術的には可能であるようにも思われる。しかし、日本の原子力はIAEAの監視下にあることと、そしてなにより平和憲法のもとに戦争放棄を宣言し、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した(憲法序文)」日本国民にはとても核兵器開発はあり得ないだろう。 このような国際的会合に出ることのメリットの一つとしては、各国参加者の異なった視点に触れられることである。なかでも興味深く拝聴したのは、Pangea Resources社のプロジェクトである。これは使用済み核燃料の最終処分サイトを建設し、契約により各国から核廃棄物・使用済み核燃料を受け入れるというものであった。「契約」という合理的発想の元に、自国の核のゴミを他国で処分するという発想は、日本人の国民性と相容れないように思えるが、日本が海外委託で再処理を行ってきたことと、現実に核燃料サイクル処理能力が使用済み燃料発生量に追いつかないことを考えると、Pangea Projectも将来日本にとって選択肢の一つとなり得るかもしれないと思う。 今回のワークショップには、Calvert Cliff原子力発電所の見学が含まれていたが、これも非常に興味深かった。 まず警備の厳しさが目立ち、車両による突入を妨げる防護や、警備員の銃器携帯が印象的であった。そして日本と違いIAEAによる監視がなく、見学者を原子炉建屋に立ち入らせないという違いがあった。これは核兵器保有国の原子力発電所については、いまさら使用済みウラン・プルトニウムから核兵器転用を懸念しなくてもよく、放射線被曝の危険性をいたずらに高めないために原子炉建屋には立ち入らせないということらしい。原子力を安全に商用利用していく上で、IAEAやWANOに対する透明性の拡充は必要であると考えられ、こういった米国原発の不透明性は改善されるべきと思う。 東電を始めとする日本の原子力業者、台湾電力、KINS(韓国)は、CSCAPウェブサイトのモニタリングデータ公開に賛同しているが、プロジェクトの中心である米国の情報公開が立ち後れているようでは、今後このほかのCSCAPメンバーに協力を広めていく過程では困難が予想される。 それでも原子力情報の一般公開は、原子力エネルギーへの信頼を高める上で有効であり、その効果は昨年のJCO事故時に情報公開を推進していたJNCへの評価の高さからも理解できる。このプロジェクトが軍事的安全保障問題にどう絡んでいくかは分からないが、CSCAPのような政策提言体が、具体的なプロジェクトを推進することは、活動の活性化において効果的と考えられるため、今後もこのプロジェクトの推進に協力していきたいと考えている。 (太平洋経済協力会議(PECC)日本委員会事務局長代理)
|