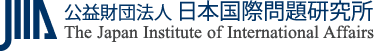CSCAP北太平洋作業部会 第6回会合の開催 (菊池 努)
平壌で歴史的な南北首脳会談が開催された直後の6月16、17の両日、CSCAP(アジア太平洋安全保障協力会議)北太平洋作業部会の第6回会合がウランバートルで開催された。会合には山本吉宣(東京大学教授)、ブライアン・ジョブ(カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学教授)両共同議長のほか、日本・米国・中国・ロシア・モンゴル・韓国・北朝鮮・インド・インドネシア・シンガポール・ニュージーランド・欧州連合・ベトナム・フィリピンの各委員会から専門家が参加した。また台湾からも専門家が出席した。日本からは小澤俊朗CSCAP日本委員会事務局長(当研究所所長代行)ほかが参加した。 会合では、「大国間関係」「核・ミサイルの拡散」「朝鮮半島問題」「経済(エネルギー)協力」の四つのテーマについて、共同議長より問題提起がなされた後、活発な議論が展開された。以下、その概要である。 第一に、アジア太平洋における対話・協議の枠組みに関する問題である。今回の会合で関心を呼んだものの一つは昨年末に実現したASEAN+3(日中韓)の機能と役割である。スワップ協定の締結などにみられるようにASEAN+3の機能を、APECを始めとするアジア太平洋の重層的な地域協力の枠組み作りの一環として評価する意見と、このフォーラムの将来ビジョンが現状では不明確であること、大きな紛糾を呼んだEAECと参加国が同じであること、等に由来する将来への懸念も表明された。また、ASEANなどの中小国にとっては、ASEAN+3は、大国の変化(たとえばアメリカのアジアからの「撤退」と中国の「台頭」)に備えた措置(hedging strategy)の一環であるとの指摘もあった。 朝鮮半島の平和の問題を協議するフォーラムに関しては、「朝鮮民族自身による朝鮮問題の解決」を指摘する一方で米朝間の協議の重要性を引き続き強調する北朝鮮と、南北間の直接の対話を重視する日米韓、4者協議の役割を重視する中国、6者協議フォーラムの設立を求めるロシアとこれに否定的な北朝鮮等、立場の相異は大きい。 また、6者協議に意義を見いだす諸国の間でも、その役割についての認識は一様ではない。平和体制の問題を含む朝鮮半島全般の問題を議論すべきであるとするロシアと、平和体制の樹立など朝鮮問題の将来に直接かかわる問題については南北および4者協議で取り扱い、経済協力や環境問題など北東アジア全体にかかわる問題を6者協議で取り扱い、4者協議と6者協議との間で機能的な分業を行うべきであるとする韓国の立場がある。また、朝鮮半島の軍事的緊張を緩和するための措置を検討するために米+韓国+北朝鮮の3者協議を開始すべきであるとの提案もあった。これに対し韓国の参加者からは、朝鮮半島のみを対象とした軍縮提案は受け入れられない、朝鮮半島の軍事問題は北東アジアというより広い文脈で議論すべきだとの指摘もあった。 第二に、朝鮮半島問題に関しては、南北首脳会談の開催を契機に南北間の緊張の緩和と対話・協力の進展(南北の共存)の可能性を指摘する声がある一方で、共同声明が経済協力や離散家族の再会問題など、短期間のうちに実現可能なものに焦点をあて、92年の南北基本合意書の取り扱いや平和協定など朝鮮半島の将来の問題に言及していないことから、今後の南北間の対立の可能性を指摘する意見もあった。 また、北朝鮮の加盟の実現により、ARFはアジア太平洋の地域フォーラムとしての機能を果たす条件を満たしたことになり、とくに北東アジアの問題を議題のなかに組み入れる努力が重要であるとの指摘があった。その一方で、北朝鮮の参加者からは、北東アジアを対象とした政府間フォーラムでの安全保障問題の討議に消極的な意見も出された(北朝鮮の参加者は、北東アジアの地域的な安全保障問題は当面、CSCAPのような場で協議するのが望ましいとの意見を表明した)。会議ではまた、朝鮮半島の統一方式での南北双方の立場の表明があった。「現状維持」を事実上相互に支持しつつも、「統一」を唱えざるをえない分断国家の宿命を感じた。 なお、北朝鮮の参加者から、南北首脳会談の実現に中国が大きな役割を果たしたことを感謝するとの発言があった。これまでのCSCAP会合では北朝鮮代表は中国と距離をとっているとの印象が強く、中国に対する積極的評価はもとより、中国の役割それ自体に言及することもほとんどなかった。しかし、金正日総書記の中国訪問を経て、中国の役割に対する高い評価が初めてなされたことは、最近の両国関係の改善を示唆するといえよう。韓国の参加者からも南北関係の今後に中国が重要な役割を果たすことになろうとの指摘があった。また、中国の参加者からは、最近の北朝鮮の外交イニシアティブを高く評価する発言がなされ、金総書記の訪中に際して同書記が中国の経済改革に関心と支持を表明したとの紹介があった。 余談だが、当初北朝鮮の参加者からは「朝鮮半島は緊張に満ち満ちている」との趣旨の論文が配布されていたが、会議当日の報告ではこれに一切触れることなく、「(朝鮮)情勢は劇的に改善された」との趣旨の報告を行った。南北間の対立よりも改善を強調する姿勢が印象的だった。 第三は、この地域の安全保障環境をどのようにみるか。議論の中心はNMD、TMD問題である。中国の参加者からは、この地域は全般的に緊張緩和に向かっているとの認識が表明される一方で(「緊張」よりも「緩和」「改善」の側面を強調)、NMD、TMDに関しては厳しい批判が日米に向けられた。ロシアの参加者からもアジア全体に軍事力の増強というきわめて危険な兆候がみられるとの発言があった。 また、欧州からの参加者もNMD、TMDの開発がABM条約や国際的な不拡散体制へおよぼす悪影響を懸念する意見が表明された。NMD、TMDに関しては賛否両論があったが、議論の混乱もみられ、日本からの参加者よりNMD、TMDに関する議論を整理する発言がなされた。なお、日本の参加者よりTMD開発に対する日本の基本的立場の説明がなされ、TMDの保有が現行の専守防衛政策を維持強化する一環であることが強調された。 これに関連して、米国からの参加者からは、(中国など)弾道ミサイルなど攻撃的な兵器の開発を熱心に進めている諸国が、NMDやTMDなどの防御型兵器の開発に反対するのは奇妙であるとの指摘もあった。また、中国の核ドクトリン・核配備の現状の不透明さが指摘され、透明性の向上を求める意見もあった。米国からの参加者より、NMDに関する米国内の議論、日米・米欧関係への影響等について説明がなされた。台湾からの参加者からも新政権の対TMD政策について説明があった。 なお、TMD開発に対する韓国の立場は微妙である。自国の直近に脅威を抱えている韓国はTMD配備に関心がないとして日米のTMD研究への参加を見送ったが、low tierのTMDを配備する可能性は高く、その動きはすでにPACⅢの導入に示されているとの指摘があった。 第四に、本作業部会ではこれまでも経済協力の問題を多角的な観点から議論してきたが、今回は新潟でエネルギー問題を中心に地域協力のあり方を研究しているロシアの学者を招き、エネルギー協力の可能性について議論した。ユーラシア大陸の内部に埋蔵する巨大なエネルギー資源は、関係諸国の対立を激化させる要因ともなりうるし、地域協力を通じて地域の平和と安定に結びつけることもできる。 いかにして後者を実現するか、今後さらに検討すべき重大な問題である。 本会合はこれまで年に1回の開催が通例であったが、朝鮮半島情勢の急展開に鑑みて、次回会合は、CSCAP国際運営委員会の機会を利用して12月9日にマニラで開催する予定である。 (アジア太平洋研究センター客員研究員)
|