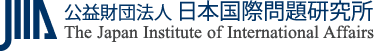CSCAP国際運営委員会およびアジア太平洋ラウンドテーブル (中山 俊宏)
CSCAP(アジア太平洋安全保障協力会議)第13回国際運営委員会(6月2❹3日)および第14回アジア太平洋ラウンドテーブル(3日❹6日)がクアラルンプールにて開催され、山本吉宣東京大学教授、小澤俊朗当研究所所長代行、菊池努当研究所客員研究員(青山学院大学教授)、筆者が出席した。 CSCAP第13回国際運営委員会 設立以来13回目を迎える運営委員会であったが、これまでの功績を認めつつも、今後のCSCAPの役割について多くの議論が取り交わされた印象深い会合であった。まず新たにインド、パプアニューギニア、カンボディアが加盟申請をし、いずれも幅広い層から構成される国内委員会を設置したことが認められ、満場一致にて可決された。これでCSCAPのメンバー国数は20ヵ国となり、CSCAPが設立以来掲げてきた協調的安全保障の概念がアジア太平洋地域においても確実に根づいていることを印象づけた。また、ハン・スンジュ共同議長(韓国CSCAP)の任期終了に伴い、豪州CSCAPのデスモンド・ボール教授が新共同議長として指名を受け、満場一致にて可決された。CSCAP共同議長には、ASEANおよび非ASEAN諸国から1名ずつが就任することが慣例化しており、ASEAN側の議長は、任期がもう1年残るCSCAPフィリピンのキャロライナ・ヘルナンデス委員長が引き続き務めることになる。 CSCAPは、信頼・安全醸成措置WG、総合安保・協調的安保WG、海洋協力WG、北太平洋WG、国際犯罪WGにおいてそれぞれ専門家が集まり、多面的に安全保障の問題に取り組むべく努力しているが、このWGが取り上げる議題を含めて総合的なオーバーホールが必要ではないかとの意見が表明され、今後の課題とすることとなった。現在、CSCAPのメンバー国のなかには、大きく分けて、ARF(ASEAN地域フォーラム)の議題と歩調を合わせ、よりトラック・ツー色を高めるべきだとの議論と非公式なアカデミック・インスティテューションとしての独自性を打ち出し、ARFが政府間協議であるがゆえに取り上げない、もしくは取り上げられない議題を野心的に導入すべきだとの議論がある。設立当初とは異なり、アジア太平洋地域における安全保障のあり方の総合的なヴィジョンを提供する段階から、より細部に分け入った議論が要請されるようになったいま、今後のCSCAPの方向性を模索するなかで生じたある種の路線論争といえよう。 今次運営委員会の地域安全保障に関するサブスタンシャル・セッションにおいては、「朝鮮半島情勢とその地域的インプリケーション」につき討議が行われた。韓国と北朝鮮のプレゼンテーションに続いて、日本、米国、中国からコメントが行われたが、南北首脳会談の開催を前にして、各者とも自国の公式見解を踏襲する見解を表明したにとどまり、必ずしもトラック・ツーの柔軟性が生かされたとはいいにくい。このような機微な問題だからこそ、トラック・ツーの柔軟性が生かされるべきであり、この種の議題につき活発な議論をいかに展開できるかが今後のCSCAPの活動のカギとなっていくであろう。ARFへの北朝鮮の参加によって、CSCAP独自のカラーが一つ失われることになるが、北朝鮮を国際社会の一員として積極的に巻き込んでいく場として逆に役割が高まったと考えることもできよう。 第14回アジア太平洋ラウンドテーブル 本ラウンドテーブルは、毎年この時期に200名を超すアジア太平洋地域の戦略・安全保障の専門家が一堂に会する恒例の会合で、14回目を数える。インド・パキスタン核実験、アジア経済危機に焦点が絞られた一昨年のラウンドテーブル、コソボ危機、インドネシア情勢に焦点が絞られた昨年のラウンドテーブルと比較し、今次ラウンドテーブルは、目前の「ホット」な危機が不在であったことから若干焦点のぼやけたものとなった感は否めない。 「グローバリゼーション」が中心的なテーマの一つであったことは疑いないが、そのインパクトの強さは誰もが認知しているものの、その具体的な意味、インプリケーションについてはまだ対立軸さえ明確に描けていないのが現状であり、アジア太平洋地域におけるグローバリゼーションの安全保障上のインパクトについての考察は今後の課題といえよう。 TMD、NMDについても若干の議論はあったが、とくに際立った激しい議論はなされなかった。今回目新しかった点は、コンカレント・セッションにて、「人間の安全保障」「市民社会」が取り上げられ、前回までコンカレント・セッションで扱われていた「ジェンダー問題」がプレナリーに格上げされたことにみられるように、アジア太平洋地域においても広く市民社会の問題に大きな関心が集まったことがあげられる。 しかし、これらはまだ本地域に根づいているとはいえず、まだその多くがきわめて脆弱であり、この新しいイッシューへの注目が伝統的な安全保障の軽視につながるような事態は避けなければならないであろう。 事実、「軍事バランス」のコンカレント・セッションでは、昨年よりも突込んだ意見交換が行われ、来年はプレナリーで取り上げられるべきだという声が多かった。 (アメリカ研究センター研究員)
|