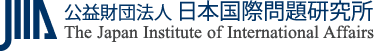CSCAP第14回国際運営委員会
中山 俊宏
さる12月11日、マニラにてCSCAP第14回国際運営委員会が開催された。今次運営委員会には、前回の運営委員会で新たに加盟したインド、パプアニューギニア、カンボジアを含む、CSCAP全加盟国が出席した。CSCAP日本委員会からは、松永信雄・委員長(JIIA副会長)、山本吉宣・北太平洋作業部会共同議長(東京大学教授)、小澤俊朗・事務局長(JIIA所長代行)、菊池努・JIIA客員研究員(青山学院大学教授)ほかが出席した。
国際運営委員会は、CSCAPの最高意思決定機関として、CSCAPの活動全体を統括する権限を、CSCAP憲章(http://www.cscap.org/charter.htm)によって付与されている。現在、運営委員会で懸案となっているのは、本ニュースレターでも随時報告している通り、今後のCSCAPの進むべき方向性である。
これは、すべての参加国が、納得のいくペースで議論をすすめていくべきであるという配慮の精神と、トラックⅡの柔軟性を生かし、政府間対話では取り上げにくい問題に積極的に踏み込み、ASEAN地域フォーラム(ARF)に新たな方向性を示すべきだという積極活用方針の間のバランスを探ろうとする試みであると言い換えることもできよう。右との関連で、これまでとかく、回避しがちであったミサイル防衛に関する議論など、軍事的な安全保障問題についても、CSCAPとしてより積極的に踏み込んでいくべき時期ではないかとの意見も表明された。
このような方向性に関する議論を本格化させるべく、CSCAPの実質的な討議の場である国際作業部会(海洋協力WG、国際犯罪WG、包括的安全保障WG、北太平洋WG、信頼醸成措置WG)のレヴューを行う特別グループが結成されることとなり、今春同グループの会合が開催されることとなった。
配慮の精神と積極活用の間のバランスをいかに見いだしていくか。多国間安全保障対話の枠組み設立そのものが目的であった創設期から移行しつつあるアジア太平洋地域において、CSCAPのオーバーホールを行うレヴュー・グループが設立されたことの意義は大きい。
(アメリカ研究センター研究員)

|