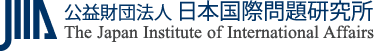|
視点 Point of View
―CSCAP― 直面する壁をのりこえられるか
小澤 俊朗
CSCAP(シースキャップと発音する)は、アジア太平洋地域の安全保障問題に関する協力を推進する民間の国際組織であり、民間レヴェルでのいわゆる「トラックⅡ外交」(トラック・トゥーと発音する)の場を提供している。「トラックⅡ外交」とは、民間研究機関と大学の研究者を中心とする会合に、一部政府関係者が個人の資格で出席し、それぞれが自国の政府の立場に固執することなく自由に意見交換するという態様の「民間外交」のことを指す。「アジア太平洋安全保障協力会議」と訳されるCSCAP(Council for Security Cooperation in the Asia Pacific)の活動は、すべて英語で行われている。
〔沿革と背景〕
1989年11月にベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦の終結を迎えていくなかで、アジア太平洋地域の安全保障の枠組みについても再検討すべきではないかという声が高まった。米国を中心とするいくつかの2国間安全保障条約体制が地域の安定に貢献していると認識する一方で、地域レヴェルで信頼を醸成し、政治安全保障問題に関する対話を推進して安全保障面での多角的な協力関係も構築していくべきだという考え方が強まった。このような考え方は、91年7月のASEAN拡大外相会議における中山太郎外相(当時)のスピーチによく表れている。
1991年から92年にかけて、ASEAN戦略国際問題研究所連合(ASEAN ISIS)、日本国際問題研究所(JIIA)、米国戦略国際問題研究所(CSIS)太平洋フォーラムと韓国ソウル・フォーラムの関係者は、このような問題意識をもってたびたび会合し、アジア太平洋地域の安全保障問題に関する協力を推進する民間の国際組織づくりに努力した。その結果、93年6月にCSCAP設立宣言が発表されるに至り、同年12月には、ロンボクに10カ国の研究機関の代表が集まり、CSCAP憲章を採択し、国際事務局をクアラ・ルンプールに設立することなどを合意した。このなかで、各研究機関の代表は、研究者と有識者に政府関係者を交えた国別委員会を設立することをコミットし、94年6月には、10カ国の国別委員会が集う形で第1回CSCAP会合が開催された。CSCAP設立の過程が、政府間の安全保障協力対話の場であるASEAN地域フォーラム(ARF)設立(94年)の過程に大きな影響を与えたことはいうまでもない。
〔活動内容〕
主たる活動は、5つの作業グループを中心に進められている。作業グループの成果で運営委員会が有用であると判断したものは、ARF議長に送付されており、また、いくつかの出版物も刊行されている。CSCAP活動の概要と成果はインターネットに公示されている。(http//www.cscap.org/)
「信頼醸成措置(CSBM)」作業グループは、もっとも活発に活動している作業グループであり、「アジア太平洋安全保障信頼醸成措置」に関する報告の提出などいくつか良い成果を上げている。最近は、民生用原子力利用と不拡散の問題や予防外交について会合を重ねている。「海洋協力」作業グループは、「地域的海洋協力に関するガイドライン」報告をとりまとめ、「海洋における法と秩序に関する協力」という報告書を発出しようとしているところである。
日本は、カナダとともに「北太平洋における安全保障協力」作業グループの幹事国を務めている。この作業グループでは、山本吉宣・東京大学教授がブライアン・ジョブ・ブリテッシュ・コロンビア大学教授とともに議長を務める形で、朝鮮半島をめぐる諸問題を中心に対話が進められている。この作業グループには、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の軍縮平和研究所が毎回出席者を出しているので、しばしば議場外で個人レベルの「南北対話」や「日朝対話」が行われる。筆者もこの作業グループに毎回出席しており、北朝鮮代表と打ち解けた雰囲気で話をすることを楽しみにするようになってきている。
台湾は、国別委員会としてCSCAPに加盟していないが、作業グループ活動に個人資格でオブザーヴァー参加ができるとの申し合わせがあり、各作業グループ活動に積極的に参加している。しかし、会議のなかで台湾海峡問題を直接取り上げることはできないので、もどかしさを感じているように見受けられる。そうはいっても、やはり議場外ではしばしば個人レベルの「海峡対話」などが行われており、これがトラックⅡ外交の良さであろう。
〔課 題〕
民間国際組織のCSCAPは、政府間組織のARFで公式に取り上げにくい事項を取り上げて、アジア太平洋地域における信頼を高めていくという役割を果たすことが期待されている。この点では、評価できる成果があるとはいえ、大きな課題に直面しているといわざるを得ない。
CSCAP設立後、中国と北朝鮮をいかに取り込んでいくかという問題があった。中国については、台湾海峡問題を取り上げないこと、台湾からの参加は個人資格として作業グループのみに止めること、という中国側が出した条件をCSCAP側が受け入れる形で中国のCSCAP加盟が実現した。また、北朝鮮については、ひとつの研究所のみで国別委員会に該当するということが認められた。
両国をはじめとするいくつかの国別委員会は、主権尊重を強く主張し、内政不干渉原則を盾に議論の展開を阻むことがあるので、CSCAPの枠内では学術的視点から十分掘り下げた議論を進められないことがある。たとえば、「南シナ海」の問題は、本来CSCAPで取り上げていくのにふさわしい問題であると思われるが、中国側の主張のために議論できないでいる。会合を重ねるにつれ、中国と北朝鮮の国別委員会の代表たちはずいぶんと会議慣れし、用意したペーパーから離れて、当意即妙な対応を見せるようにもなってきている。彼らからもCSCAPを盛り立てていくという意向が感得できるようになってきているが、トラックⅡ外交といえども、いわゆる「機微な」問題については率直な対話が難しいという現状にかわりはない。
2000年に入って、インド、カンボジアとパプアニューギニアの国別委員会の加盟が認められ、CSCAPに加盟している国別委員会数は20となった。CSCAP設立時点での10の国別委員会の意欲が、その後に加盟した10の国別委員会に本当に共有されるようになるまでには、まだまだ時間を必要としているといえよう。
運営委員会では、CSCAP活動を一層活性化させていくための工夫についての議論が開始されており、作業グループの改正や幹事国の入れ替えを含め、いろいろな見直しが検討されていく予定になっている。筆者もその過程で努力していきたいと考えている。
(CSCAP日本委員会事務局長)
【CSCAP日本委員会について】
CSCAP日本委員会は、1994年4月に設立され、委員長に松永信雄・日本国際問題研究所理事長(当時)を選出した。現在35名が委員に登録されており、年に1−2度会合している。CSCAPの設立過程から日本国際問題研究所が深く関与していたこともあって、日本委員会の事務局は日本国際問題研究所が務めることになっている。事務局長は、日本CSCAP委員長と協議しつつ、どの会合に誰が出席すべきかなどを調整している。また、CSCAPにおける議論の方向が外務省、防衛庁を中心とする関係省庁に十分フィードバックされるように、日本国際問題研究所で行われている各種の研究会で、関係者を交えた会合が開催されている。 |

|