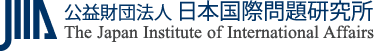CSCAP「北太平洋作業部会」第3回会合[千葉・幕張] (菊池 努)CSCAP(アジア太平洋安全保障協力会議)の作業部会会合が、97年12月15-16の両日、千葉県の幕張において開催された。97年1月のカナダ(ヴァンクーバー)での会合に続く第3回目の会合である。この会議には、日本、豪州、カナダ、中国、インドネシア、北朝鮮、韓国、ニュージーランド、フィリピン、ロシア、タイ、ベトナム、アメリカの各委員会から代表が参加した。 また準加盟のEU(欧州連合)委員会からも参加があったほか、さらには台湾、KEDO(朝鮮半島エネルギー機構)からも専門家が個人の資格で参加した。関係のメンバーが一堂に会した「フル・ハウス」会合としては前回のカナダ会合に続いて2回目である。 会議では、当作業部会の山本吉宣(東京大学教授)、ポール・エバンス(カナダ・ヨーク大学教授)両議長の司会のもとに、「北東アジア情勢」、「アジアの国境CBM(中ロ、中印、中ロ南アジアの国境での信頼醸成措置)」、「北束アジアの経済協力」、「北東アジアの安全保障とARF(ASEAN地域フォーラム)の役割」をテーマに活発な議論が展開された。 北東アジア情勢に関しては、KEDOの活動の進展、四者会談の開始、日米中露四大国間の頻繁な首脳会談の開催にみられる二国問べ一スの関係改善など、地域の安定にとって好ましい展開が最近見られたものの、他方でアジア各地を襲う通貨・経済危機が地域の政治的安定に悪影響を及ぼすことへの懸念が表明された。とりわけ韓国の通貨危機は、KEDOの活動や北朝鮮への経済支援等に深刻な影響を及ぼす可能性を秘めており、また、これまでの韓国企業の活発な海外進出を考慮すれば、進出先の中国やロシア 経済への悪影響も懸念される。また、これまで混乱を回避してきた中国(国際経済への中国の統合が十分に進展していないことの証左でもある)にもアジア経済の混乱は影響するものと思われ(投資の減退、輸出競争力の低下、香港株式市場の動揺と国営企業改革へのマイナス効果など)、その政治・安全保障上の影響が懸念される。 国境CBMに関しては、当初論文報告を予定されていた準加盟のインドの参加者が急用で不参加になったが、主に中国の国境部でのCBMについて、中国、ロシア、モンゴルの参加者より報告があった。国境CBMについては、その内容とそれぞれの関係諸国の意向・期待について必ずしも外部に明らかになっていなかっただけに、これらの報告は有意義であった。また、海上CBMへの適用の可能性が議論された。 経済協力に関しては、北朝鮮が進める自由貿易地帯構想について報告、議論があったほか、北東アジアの経済協力を前進させるために、太平洋協力の運動を先導してきたPECC(太平洋経済協力会議)の北東アジア版を検討すべきであるとの意見も出された。なお、必ずしも経済協力を扱ったものではないが、朝鮮半島情勢とりわけ四者会談について、r体の参加者より四者問の相互関係を詳細に分析した密度の濃い論文が提出され、会議参加者より高い評価を得た。 ARFに関しては、モンゴル、北朝鮮の参加の可能性、北東アジアのCBMを促進する」二でのARFの役割、ASEANの経験の北東アジアヘの適応の妥当性などが議論された。また、政府間協議を支える北東アジア諸国の戦略研究機関の間の提携の可能性についても検討された。 今回の会議は、アジア各地を通貨危機が襲うという、前回の会合の際には予想もされない事態の急展開の中で行われ、この結果、その安全保障上のインプリケーションに強い関心が寄せられた。とりわけ韓国の直面する経済的困難は、これまでの朝鮮半島をめぐるさまざまな試みの前提になっていた韓国の政治・経済的安定を著しく損なう可能性を秘めたものであり、地域全体への通貨危機の影響とともに今後さらに深い検討が不可欠であろう。 今回の会議で朝鮮半島を安定化させる「秘策」が生み出されたわけではないが、南北朝鮮のほか、日本、アメリカ、中国、ロシア、台湾などのこの地域に深くかかわる関係者が一堂に会する会合としては本会合はおそらく世界で唯一のものであり、慎重な運営を通じて「対話の慣習」造りに貢献できればと思う。 なお、今回の会合の機会を利用して、KEDOからの参加者を交えてKEDOの活動の現況、また韓国からの参加者を交えて数日後に予定されていた韓国大統領選挙についての非公式懇談会が開催された。関係者の厚意に感謝したい。今回の会合に提出された論文は、会議での議論の要旨とともに、明年春を目途に当研究所でまとめられる予定である。 (アジア太平洋研究センター客員研究員)
© 2000 財団法人日本国際問題研究所
〒100-6011 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ビル11階 |