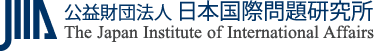|
今回の米大統領選挙キャンペーンには、イラク問題を除いて外交問題が争点とならないといった特徴がある。この主な理由としては、イラク情勢が以前より安定したことにより、争点がサブプライム問題を中心とした経済問題にシフトしたことが挙げられる。そのためか、クリントン、オバマ、マケインといった三大候補者の外交政策に関するスピーチの内容にはあまり一貫性が見られない。これまでのオバマとクリントンの外交政策スピーチの内容をみると、この二人が政権の座についた場合、米国はタカ派的な外交政策を展開する可能性がある。特にクリントンは女性という弱いイメージを払拭しなければならないため、クリントンが大統領になった場合には、そのような傾向は強まるかもしれない。また両民主党候補者は、環境や労働者権利の保護という観点から自由貿易の推進に批判的であるため、北米自由貿易協定(NAFTA)の見直しを指示する可能性がある。
マケインは、セオドア・ルーズベルトの棍棒外交(Speak softly and carry a big stick)をイメージさせる非常に興味深い外交政策スピーチを行った。マケインは、ブッシュ政権の一国主義を批判し、同盟国と連携することの重要性を主張しているが、これはマケイン外交のソフトな面(Speak softly)を表している。また、マケインは一貫してイラク派遣軍の増派を主張しているが、これはマケイン外交の攻撃的な面(carry a big stick)を示唆するものである。マケインの外交政策方針で驚くべき点は、ロシアに対する強硬姿勢である。マケインはロシアをG8から締め出すべきなど過激な主張しているため、マケインが大統領になった場合、米露関係は現状より悪化する可能性がある。
今回の大統領選挙キャンペーンでは、日本は議論の対象になっていないため、次期米政権において日本がどのように扱われるかは分かりにくいものがある。ブッシュ政権は、日本に対して「Reassurance Diplomacy(安心外交)」を展開し、日米同盟の重要性を常に指摘してきた。しかし、近年、米国の北朝鮮政策の方向性に対して日本国内に不信感が芽生えるなど、米国の安心外交の信頼性は崩れ始めているように思える。日本国内には、民主党が政権をとった場合、米国は日本を見捨てて中国に接近するのではないかという疑念が存在するが、次期米政権はこのような日本の懸念を払拭する努力をすべきであろう。そのために次期米政権は、早い段階に日米首脳会談を開き、日本が「見捨てられ」に対してヘッジ的な行動をとらないように、米国の日本及び東アジアへの軍事的関与を再確認するべきである。また米国は、日本と共同で不拡散や環境などグローバルな問題に取り組んでいくべきである。
日本は、ODAやPKO活動を通して国際社会における自国のプロフィールを高める努力をするべきである。日本は、伝統的にODA大国であるが、PKOの分野においてももっと積極的な活動をするべきである。また日本は、気候変動やその他環境問題の分野においてソフト・パワーを有しているので、これを積極的に活用すべきである。現在、日本の国内政治は「ねじれ国会」により混乱しているが、国会の膠着状態を早期に解決し大きな政治的リーダーシップを発揮することができる政治体制を整えるべきである。
|