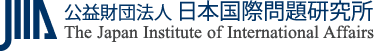|
今回の日本訪問では、皇太子殿下、麻生首相、中曽根外務大臣他と会談ができ、とても感謝している。昨日の外務大臣との会談では、世界の政治情勢と国連改革についての意見交換を行った。国連は国際平和と安全保障のための唯一の国際組織であるが、設立から60年間変わっておらず、いくつかの点で改革が必要であるという日本の主張にアゼルバイジャンも賛同する。また日本の国連安保理常任理事国入りに対して、アゼルバイジャンとしても支持することを表明した。さらに、アゼルバイジャンの重要な地域問題のひとつである、南コーカサスにおけるアゼルバイジャンとアルメニア間のナゴルノ・カラバフ問題についても両国の外相会談において議論した。日本が他の国連加盟諸国と同様に、停戦調停の際の和平案を重視して領土・国境問題についてアゼルバイジャンの見解を支持してくれていることに感謝している。
本日はアゼルバイジャンの外交政策の上で重要な優先課題、地域の安全保障と繁栄についてお話したい。アゼルバイジャンは、アルメニアとの紛争、政治的安全保障の問題、エネルギーを含む経済問題、グローバリゼーション下の新たな脅威等の問題を抱え、慎重に外交政策を立案している。アゼルバイジャンの地理的な立地条件をイメージしてもらいたい。中央アジアと欧州の間の接合点に位置し、北にロシアと、南はイランと国境を接し、カスピ海があり、豊富なエネルギー資源がある。このことを踏まえれば、わが国は、中央アジアからのエネルギーをグルジア、トルコへ輸送する南コーカサス地域におけるコリドール(回廊)の役割を果たしていることがお分かりになるであろう。わが国の外交政策のもうひとつの側面は、天然資源である。石油と天然ガスを有している一方で、地理的位置関係をみれば、その資源をどのように供給するか、どの国際市場に供給するかが、外交課題として問われることになる。もうひとつ指摘しておきたい点は、わが国の宗教構成はイスラム教徒が多数を占めているが、異なる宗教に対しても寛容で、文化の架け橋としての役割を担っている。すでに100年近くもの間、850万の人口を擁するアゼルバイジャン国内には様々な宗教を信仰する民族が平和裡に共存してきた。
アゼルバイジャンの外交優先課題をさらに掘り下げて、わが国の発展という側面で見てみると、最大の懸案問題は我々の領土を完全に回復すること、すなわち国土回復問題である。我々は隣国アルメニアとこの問題について様々なレベルで交渉しているところで、特に二国間の外相会談、首脳会談において重要な話し合いを行っている。実際に、ソ連崩壊後、アゼルバイジャンの支配下にあったほぼ20%の領土においてよく知られる民族浄化が起こった。そのため現在この領土には、ただ一人のアゼルバイジャン人も住んでおらず、アルメニア人以外のいかなる民族も住んでいない。さらにいえば、例えばナゴルノ・カラバフ地域は、アゼルバイジャン領であった。この地域とその周辺の7つの行政区が占領され、現在アルメニアの支配下にある。同地域ではアルメニア人とアゼルバイジャン人は、かつては平和に共存していたが、民族浄化が行われてしまった今ではアルメニア人だけが住んでいる。鉄道や道路も破壊され、この地域のあらゆるコミュニケーション手段が寸断されてしまった。この問題は我々にとって最大の懸案であり、平和的な問題解決こそがわが国の外交政策の主要課題である。我々と隣国アルメニアとの間で、双方にとって利益となるような説明ができるように、そして早急にこの地域で、経済発展や繁栄、政治的な安定がもたらされ、将来の展望を切り開くことが可能となるように和平を実現することが、わが国および南コーカサス地域全体にとっても非常に重要である。
もうひとつのわが国の外交優先課題は、国際平和を促進するためグローバルな安全保障に対してアゼルバイジャンも国連加盟国として貢献することである。例えばアフガニスタン、イラク、コソボなどで、様々な国連の平和維持活動が行われているが、我々も国際的な法秩序の安定化に貢献したいと考える。アフガニスタンには治安維持活動だけでなく、さらに大きな役割を果たしたいと考えている。例えばアフガニスタン再建のため、市民社会の構築、社会インフラ整備、たとえば学校や幼稚園の設立のための資金援助や、ビジネスの復活、企業支援に資金援助をするといった形でも国際平和と安全保障に貢献したいと考える。もちろんアゼルバイジャンは、他の国際機関、例えば欧州のOSCE(欧州安全保障協力会議)、GUAMやCISのメンバーでもある。それゆえ、これらのチャンネルを使って、わが国と欧州大陸との協力関係を強化することにも発展させていきたい。そのためには、わが国の国内改革を促進させる必要がある。欧州諸国を手本に学びながら、民主主義的なアプローチによって、人的能力の向上、市民社会の創設、法の秩序を強化し、独立国として国と国家の主権を強化することが重要である。
わが国の外交政策上、特に持続的な発展にとって決定的な役割を果たしているのは、欧州地域へのエネルギー供給とエネルギー輸送のための経路になることである。国際舞台でエネルギー外交をどのように促進し、国益に結びつけるかはアゼルバイジャンの発展にとって非常に重要である。エネルギー資源が経済発展の重要な要素となってから、約1世紀がたつ。最初に世界のエネルギー生産をリードしたのは、ペンシルバニアの石油だけではなく、アブシェロン半島(アゼルバイジャン)の石油でもある。わが国のエネルギー資源は、19世紀半ばから開発が始まり、世界をリードしてきた。バクー市が位置するアブシェロン半島の石油生産は、バクー市と周辺地域の発展に大きく貢献し、ソビエト時代、例えば第二次世界大戦時には、ソ連軍の重要な燃料生産・供給基地となり、ナチスドイツとの戦いを支えた。1991年の独立後は、我々が慎重にエネルギー資源開発を行うことになった。1994年にカスピ海沖油田、アゼリ・チラグ・グナシェリ油田開発契約を結んだ。この海底油田は、全埋蔵量が10億トン以上であることが判明した。さらにこの海底油田には最近膨大な量の天然ガスが存在することも判明し、その埋蔵量は2兆m3以上とされている。これらエネルギー資源は、アゼルバイジャン経済に莫大な利益をもたらし、高成長をもたらす要因となっている。この13年間でアゼルバイジャンのGDP成長率は二ケタ台の規模で、2006年は35%、2007年は25%のGDP成長をもたらした。特に2004年から2008年までの4年間でGDPは倍増している。このような高度成長の背景には、アゼリ・チラグ・グナシェリの海底油田の原油採掘に加えて石油パイプラインという大規模プロジェクトの開発も預かっている。それがBTCパイプライン(アゼルバイジャンのバクー、グルジアのトビリシ、トルコのジェイハン)建設プロジェクトである。総工費4兆ドル以上の巨大プロジェクトで、輸送能力は日量100万バレル、最大稼動時には120〜150万バレルの石油を輸送する能力をもっている。今後このパイプラインはアゼルバイジャンの石油だけでなく、カザフスタンからの石油も地中海へ輸送することが計画されている。
このパイプラインに加えて、外交戦略上重要な課題は、石油資源供給源の分散化にアゼルバイジャンが寄与することである。すでにアゼルバイジャンの港から、グルジアの黒海に開かれた港につながるパイプライン、ロシアの同じく黒海の港・ノボロシースクにつながるパイプラインも重要である。さらに鉄道網も重要である。エネルギーに関してアゼルバイジャンがコリドール(回廊)となって、様々な方法を使って国際市場で利益を生み出すチャンスがいつも存在している。天然ガス供給に関しては、我々はすでにトルコ市場にBTCパイプラインと平行して走るBTEパイプライン(バクー・トビリシ・エルズルム(トルコ))を使ってアクセスしている。その先には、グルジア、ギリシャへ向かうルートもオプションとして考えられる。ギリシャから先はどのようにパイプラインを建設するか、様々なオプションが考えられる。例えば、いわゆるTGIすなわち、トルコ、ギリシャ、アルバニア、イタリアへと流れるトランス・アドリア海パイプライン、さらにイタリアからスイスへ流れる新聞報道で有名なナブッコ・パイプライン、サウス・ストリーム(ロシア、黒海、ブルガリアからさらにイタリアへと)など、実に様々な魅力的なオプションを我々は有しているのである。もちろんこれらのオプションに関してもっとも重要であるのは、輸送にかかる通過料・タリフの設定である。これはまだ交渉段階にある。ひとつ明らかなことは、アゼルバイジャンは、天然ガスを国際市場、欧州に供給する用意がすでにできているということである。このエネルギー資源によって獲得された利益は、もちろん我々の国内改革にあてることが可能である。我々はすでにアゼルバイジャンでの起業を検討している、いかなる企業に対してもワン・ウィンドウ・アプローチという新しい法を採用して、市場を開放している。このアプローチのおかげで、起業にかかるすべての手続き、登記、課税、認可等の手続きが迅速化され、すべての手続き完了までには3日以上かからない仕組みになっている。これは外資系企業に多くの投資機会を与え、アゼルバイジャンに投資しやすい環境を与え、さらにアゼルバイジャン経済のGDP成長を支えている。
IMFのデータによれば、アゼルバイジャンは2008年のCIS諸国の中で、もっとも高い成長率を記録し、2008年のGDP総額は500億ドルであった。世界的な金融危機にもかかわらず我々のGDPは成長しつづけ、今年第1四半期のGDP成長率は4.1%を記録している。特に非石油部門がGDPの40%を占めている状況下で、我々政府の優先課題のひとつは非石油部門の発展である。同部門にさらに多くの投資やパートナーが必要である。例えば国土発展のため、地理的ベネフィットを活用したインフラ部門への投資を導入したい。すでにロシアとの間、イランとの間で北と南に抜けるコリドールのインフラ整備について合意している。もうひとつは東西のコリドール、南コーカサスを通り欧州に抜けるインフラ開発プロジェクトは、10億ドル以上のプロジェクトとなる。このプロジェクトには、バクー・トビリシ・カルス(トルコ)鉄道を含む。バクー・トビリシ間の鉄道はすでに敷設されているが、グルジアとトルコ間の接続が必要で、この間の鉄道敷設のためにわが国がグルジア政府とグルジアの企業に3億2000万ドルの融資を行っている。カザフスタンと中国の間で鉄道が敷設されることを想像してみてほしい。中国からカザフスタンを通ってカスピ海に抜け、アゼルバイジャンからグルジア、トルコへ抜けるルートができることになる。このルートが、欧州の資本をこれらの地域へ流通させることも可能となる。このように我々は非石油部門でも多くの利益機会を持っている。このほかにも重要な非石油部門として、わが国の農業を挙げることができる。農業部門はほぼ100%民営化されており、政府は農業部門に対して農業用機械や肥料などで支援を行っている。この結果、わが国の農業生産も劇的に増大し、主要な市場であるロシア、ウクライナ、カザフスタンおよび周辺諸国へ農産物を輸出している。通信部門もまた大きな潜在力を持っている部門であり、政府は国内の通信設備を向上させるためだけではなく、市民社会の構築そのものにも重要であるとして、投資計画を立てている。初等・中等・高等学校4500校のすべてにコンピューターを設置し、インターネットアクセスを可能にすることを計画している。このほか諸外国への学生派遣など、将来の国の繁栄に寄与することを期待して教育プログラム改革にも力を入れているところである。
最後に日本とアゼルバイジャンの二国間協力関係についてお話したい。わが国と日本の経済協力関係は、ソ連時代の1973年に日本の家電メーカーがエアコン工場をわが国に設立したのが始まりであった。1996年−1997年には、ハイテク産業における技術協力で合意した。わが国が独立してから日本企業がもっとも活発に事業展開しているのは、エネルギー部門である。今日では10社の日本企業が、バクーに事務所を開設している。今日は、日本の財界の方々とも会談できたことをとても名誉に思っている。我々の大きな関心のひとつは、ソーラーシステム、風力発電など再生可能エネルギーの重要性である。また、わが国のような地理的条件において重要であるのは水の安定的な供給である。この分野の組織化、プラント建設、技術協力について世界でもトップレベルの技術力を誇る日本の財界の方々と様々な意見交換を行うことができたことは、非常に喜ばしいことである。2006年の大統領来日以来となる今回の私の来日によって、アゼルバイジャンと日本政府および日本企業との二国間協力がより深まることを期待する。
|