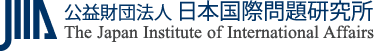|
1994年以降、アフガニスタンではタリバンが台頭した。現在では、タリバンとアル・カーイダの協力関係はよく知られているところであるが、タリバンは台頭当初、米国に歓迎されていたという事実は興味深い。これは、タリバンがアフガン情勢を安定化させるとの期待が、米国にあったからである。例えば、米国の石油会社であるUNOCALが、タリバンによる安定化達成後にアフガニスタンにパイプラインを敷設する計画を立てていた。しかし、イラン外交官殺害、学校閉鎖、女性の権利制限、アル・カーイダとの協力関係構築など、タリバンは次第にその本性を明らかにした。
2001年の9.11事件は、アフガニスタンにとって大きな転機となった。米英軍を中心とする多国籍軍の「不朽の自由作戦」の下、タリバンとアル・カーイダの殲滅を目指してアフガニスタン攻撃が始まったのだ。この作戦の目的は、短期的には制空権確保・地上作戦の実施であり、長期的にはタリバン政権打倒・新政権樹立、アル・カーイダ殲滅、ケシ栽培・麻薬取引の停止であった。しかし、面での制圧を目指す多国籍軍の作戦では、点でのゲリラ戦を主とするタリバンとアル・カーイダの作戦活動を完全に制圧することはできなかった。8年に及ぶ戦いの結果、ビン・ラーディンは未だ逃亡中であり、アル・カーイダは完全には殲滅されておらず、アフガン情勢は以前不安定で、ケシ栽培は急増している。
北部同盟司令官であった故・マスード司令官は、かつて私に対して、アフガン情勢が安定しない最大の要因はケシ栽培・麻薬取引をめぐる支配権争いにあると述べていた。2001年に200トンだったケシ収穫は、2009年には9000トンにも及んでいる。それと符合するように、アフガン情勢も不安定化している。最近、タリバン再台頭が話題となっているが、その要因としては、イラク情勢の波及、NATO・多国籍軍へのアフガニスタン人の信頼欠如、「占領」への反感、パキスタン問題、麻薬取引、政府の腐敗・非効率性などが挙げられる。今年3月、オバマ米国大統領は情勢改善のために新たなアフガニスタン政策を発表した。そこでは、アフガニスタンへの米軍増派、アフガニスタン軍・警察強化が唱えられ、パキスタンとアフガニスタンの関連付けが主要テーマとなっている。
アフガニスタンでは大統領選挙が実施中だが、カルザイ大統領再選後の課題としてしばしば話題となっているのがタリバンとの対話である。カルザイは現行憲法承認をタリバン指導者オマルとの交渉の前提条件としており、逆にオマルは外国軍撤退をカルザイとの交渉の前提条件としている。両者が相容れないことは一目瞭然であろう。そこで、最近注目を集めるのがタリバン穏健派との対話である。しかし、私はタリバン穏健派を「幻想」であると見ている。周知のようにタリバンは、パキスタン(特に情報部)の支援の下で誕生した。その遺産は今も続いている。もし、タリバン穏健派が表舞台に現れるようなことがあれば、その背景にはパキスタン情報部と米国CIAの何らかの合意の可能性が疑われよう。
最後に、私の考えるアフガン情勢安定化のための3原則を説明したい。アフガニスタン問題については、①安定化、②治安維持、③復興・開発、の3つのレベルで取り組む必要がある。第一の安定化は、専らアフガニスタン人自身の国内問題であり、国内諸勢力が協力して政治システム・権力構造を確立する必要がある。国外勢力が介入すべきではないのだ。第二の治安維持は、当該地域の周辺諸国とアフガニスタンの協力によって達成されるべきものである。第三の復興・開発は、国際社会が取り組むべき課題であり、今後はNATO・多国籍軍派遣だけによらない「新思考」が必要となる。この3つの次元でアフガニスタン問題に取り組むことが必要である。
|