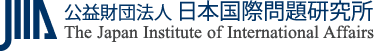|
現在の世界には、二つの相反する潮流が存在している。一つは、経済や社会のグローバル化の潮流である。インターネットなどのメディアを通して、世界中の人々がより緊密に結びつき、経済変動や食糧問題、環境問題などの影響も一国にとどまるものではない。これらのグローバルな問題に対しては、各国が協調して対処していこうという建設的な潮流が強まっている。しかし、こうした国際協調やグローバル化に対抗する危険な潮流も存在する。それが二つ目の潮流、すなわち、細分化の潮流である。特定の民族や集団の利益のみを追求するこの潮流は、世界全体の利益を追求する普遍主義に対する脅威である。こうした脅威を全世界的に及ぼしているのは、普遍主義を共有しようとしないアル=カーイダなどの非国家組織であり、また国家としてはイランである。
イランやアル=カーイダの脅威に対して、イスラエルは、価値観を共有する諸国家との協力を強化することで対抗してきた。イスラエルはWEOGの準加盟国であり、WEOGは国連において、唯一、地域単位ではなく、イデオロギーを基礎とするグループである。もちろんこのイデオロギーは、開放的で進歩的な自由と民主主義であり、各地域固有の文化を抑圧するものではない。
中東へと焦点を絞ってみると、中東は、残念ながら世界でも遅れた地域である。アジアや南アメリカ、中央・東ヨーロッパといった地域が、社会、経済、技術の各方面で急速に近代化しているのに比べて、中東の発展は遅れている。国連開発計画(UNDP)が昨年12月に発表したレポートによると、大半のアラブ諸国は最貧の状況に置かれている。この貧困が意味するのは、教育の欠如、雇用の欠如、女性の権利拡張の欠如といった多くの問題である。このレポートは、貧困の根源的な原因を、自由の欠如、機会の欠如、女性の経済活動への参加の欠如と指摘している。これらの要因が、多くの問題を引き起こしているのである。
この貧困という問題は、中東和平にも大きな影響を及ぼしている。それは、アラブ諸国がパレスチナに対する支援に真剣に取り組んでいないことである。日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国、イスラエルがパレスチナ経済に多額の援助を行っているのと比べて、アラブ諸国の援助は極めて少ない。西側諸国は、近年の経済危機で困難な財政状況に置かれている。これに対して、サウジアラビアと湾岸産油諸国は、潤沢な石油収入を得ているにもかかわらず、パレスチナ自治政府に、渋々少額の援助を与えているに過ぎない。その一方で、サウジアラビアなどは、ハマースをも援助している。ハマースは、パレスチナ自治政府の仇敵であり、イランからも援助を得ている。一部の人々は、アラブ諸国がパレスチナ支援に消極的な原因を次のように語っている。すなわち、アラブ諸国にとって、自らの後進性の原因をパレスチナ・イスラエル紛争に転嫁した方が好都合であるということである。あるいは、もしパレスチナが独立国家となり、民主主義を実現した場合、中東地域に非民主的なテロ国家や破綻国家を許容する余地はなくなる。ことのことが、非民主的な一部のアラブ諸国にパレスチナ支援をためらわせているということである。
しかし、アラブ諸国の消極性は、中東和平を阻害する主要な要因ではない。より大きな阻害要因は、イランである。イランというと、誰しも不法な核開発を思い浮かべるであろう。私は、イランにとって核開発は目的ではなく手段であることを強調したい。その目的とは、中東とそれを超えた広い地域を自己の支配下に置くことである。イランの政策を観察すると、中東の紛争に対するイランの関与を見ることができる。例えば、レバノンである。イランは、シリアを通して、シーア派テロ組織であるヒズブッラーに資金と武器を供給することで、レバノンを完全に支配している。また、パレスチナにおいても、イランは、資金、装備、テロリストを提供することでハマースを支配している。それだけではない。イランは、エジプトのムスリム同胞団や北アフリカ、湾岸諸国、イエメンの反政府組織をエージェントとして中東全域の不安定化を目指している。さらに、スーダンや中央アジア諸国、ベネズエラのチャベス政権などにも、イランは影響を及ぼしている。イランが核兵器をもてば、こうした攻撃的な政策を何の罰則も受けることなく行えるようになるであろう。
私は、イランに対して強圧的な姿勢を取ることは危険であり、対話によってのみ問題を解決すべきだと考えている人々に警告したい。そうした考えは、現実と整合しないのである。1995年にイランの不法な核開発が発覚して以来、15年にわたって我々は交渉を続けてきた。しかし、全ては無駄であった。イランの外交交渉は非常に巧妙である。イランは、民生用の合法的な核開発を行っているだけだというメッセージを表向きに発しつつ、同時に、国際社会に核兵器開発を止めることはできないというサブリミナルなメッセージも発しているのである。我々は、こうしたイランの心理攻撃に屈してはならない。核武装したイランを許容することはできないのである。
また、私は、イランや湾岸地域での緊張によって原油価格が高騰することや、原油供給の途絶を懸念する人々に警告したい。イランが核武装した場合、イランは自由に原油供給と価格を決定できるようになることを。そしてそれ以上に、彼らは核の傘のもとで、より強力に、より攻撃的にテロ組織を支援することになるだろう。さらに、イランの核武装は、核拡散防止にとって致命的である。周辺諸国は、イランのみが核武装することを許容できないからである。イランの核武装の後には、トルコ、リビア、エジプトといった国々の核開発が続くだろう。イランが北朝鮮やベネズエラと親密であることを考えれば、イランの核武装が核拡散防止体制の崩壊につながることは明白である。中東和平に対しても、イランの核武装は決定的な打撃となる。核武装をしていない現在においても、イランは、ヒズブッラーやハマース、シリアのテロ行為を通して、中東和平のあらゆる合意に反対し、和平の進展を妨害しているからである。したがって、世界の安定と中東和平の進展を望む全ての人々は、イランの核武装を許容することはできないのである。
イランの脅威を受けて、中東諸国の関係に変動が起こりつつある。中東において、イランの脅威を感じているのはイスラエルだけではなく、スンナ派アラブ諸国も同様である。あくまで非公式にではあるが、イスラエルとスンナ派アラブ諸国は、イランの脅威に対抗する協力を模索し始めている。しかし、シリアは例外である。シリアはイランと同盟を結び、イランがレバノンとガザを支配し、エジプトなどの反政府勢力を支援するために不可欠の窓口となっているのである。
イランを止めるために、日本は大胆かつ勇敢な方策を採った。日本は、国連安保理決議1929に賛成しただけでなく、アメリカやヨーロッパ諸国、韓国などと連携して、イランに対してより強い経済的・政治的制裁を科した。これによって、イランは、国際社会が真剣に核開発を止めようとしていることを理解し始めた。また、初めて核開発の代償を支払うことになった。しかし、核開発を止めるには至っていない。したがって、我々国際社会は、これまでの制裁の効果を評価し、次の手段を考えなければならない。私は、あらゆる選択肢が考慮されていることをイランに示し、より強い圧力、より効果的な制裁を科すことが必要になると考える。私は、イランに対するより強い圧力が、中東地域の安定化に大きく貢献すると確信している。
イスラエルの近隣に関しては、イスラエル政府と国民の見地から、パレスチナとの和平について話そう。イスラエル政府と国民にとって、パレスチナとの和平は戦略的な選択であるだけでなく、道義的な責務である。現在のパレスチナ自治政府は西岸のみを支配し、ガザはハマースの支配下にある。我々は自治政府との合意をガザも受け入れることを望んでいるが、ガザと西岸の分裂はパレスチナ内部で解決すべき問題であり、イスラエルが介入することはできない。イスラエルは西岸のパレスチナ自治政府と交渉し、包括的な合意と相互の実施を目指す。我々は、パレスチナ、イスラエル両国民の利益のために真の和平を結びたいと思う。真の和平とは、机上の協定や政府間の約束に留まるものではなく、両国民の真の和解でなければならない。そのためには、全ての問題を解決しなければならず、また、解決することができる。入植地の問題も、誠意と善意によって解決することができる。
入植地は和平の障害ではない。エジプトとの和平の障害ではなかったし、2005年、ガザから21全ての入植地を撤退させ、西岸からも4つの入植地を撤退させた。イスラエルは充分に成熟し民主的であり、領土、入植地、エルサレム、難民等の問題に対してイスラエル側で行える取り組みは行ってきた。しかし、これは問題の片面に過ぎない。我々はパレスチナ側からも同じ取り組みを期待する。キャンプデービット(2000年)とアナポリス(2008年)での交渉において、96パーセントまでパレスチナ側に歩み寄った。したがって、パレスチナ側も歩み寄らなければならない。パレスチナ側は、イスラエルをユダヤ人の祖国として承認し、安全を保証し、エルサレム問題や資源の共有などについてイスラエル側と合意しなければならない。また、テロ対策を検証可能な形で効果的に継続し、テロに訴えることは決してないことを示さなければならない。我々イスラエルは、あらゆる問題を前提条件無しで交渉する用意があり、パレスチナ側がテーブルに着くことを待ち続けてきた。しかし、パレスチナ側は、入植地からの撤退を交渉の前提条件として、交渉に応じてこなかった。もちろん、我々も多くの条件を持っているが、それは交渉の前提条件ではない。イスラエルは、最近10ヶ月間、入植地の建設を凍結し、交渉に臨む態度を示したが、パレスチナから反応はなかった。パレスチナ側が交渉のテーブルに着くことを願っている。
イスラエルとパレスチナの和平は、単に両国民の利益となるだけでなく、中東地域全体の利益となる。我々は中東地域全体を牽引し、世界の他の地域の発展に追いつかせたいと思っている。数ヶ月前、イスラエルはOECDに加盟した。日本がイスラエルの加盟を大いに支持してくれたことに感謝したい。日本とイスラエルは、共に天然資源に恵まれず、知的財産を活用して経済を維持しなければならない。この知識面での日本とイスラエルの連携は、両国の自然な同盟であり、世界の利益にかなうものであると確信している。
|