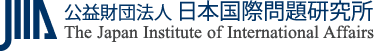|
「紛争の和平交渉の段階で法の正義を追求すれば、和平の実現が遠のく」という意見をしばしば耳にする。のちのち自身が訴追されることがわかっていながら和平交渉のテーブルに着く紛争指導者などいるはずはないというレトリックである。だが、本当に正義の追求(訴追)と和平の実現を同時に達成することはできないのだろうか。過去10年間のさまざまな地域における紛争問題を分析すれば、「正義の追求はむしろ和平の実現を促す」「平和と正義の間には補完関係がある」と結論づけられよう。
過去、大量殺戮など重大な罪を犯した指導者が訴追されたケースは多々存在する。たとえば、旧ユーゴスラビアのミロシェビッチ、チリのピノチェト、ウガンダのジョゼフ・コニー(神の抵抗軍)、スーダンのバシルなどが国内の司法当局あるいは国際的な司法機関によって訴追された。いずれのケースにおいても司法機関による訴追が紛争解決への障害となったとは確認できない。むしろ、訴追によって旧ユーゴでは残虐行為に歯止めがかかり、チリでは民政移行が進み、ダルフールの状況は良くなりつつある。
また、ボスニアやリベリアでは残虐行為を指示した指導者を訴追したことで和平交渉が前進しさえした。指導者に続いて起訴されることを恐れた周囲の人間たちが穏健化し、次々と離反していったためである。訴追をきっかけに重大な人権侵害を犯した指導者の政治力が極小化していったことが、和平への機運を高める要因になったと考えられる。これらの事例から、紛争中における正義の追求(訴追)は必ずしも和平を遠ざけることにはならないといえよう。
残虐行為を行なった紛争指導者を訴追するのではなく恩赦を与えることによって、和平交渉の席へ着かせ和解への道を探るべきだと主張する人は多い。だが、過去の殺戮行為を不問にする恩赦という方法は好ましくない。過去に重大な人権侵害を犯した者たちを和平後の新政府のなかに入れて、いったいその政府に正当性があるといえるだろうか。アフガニスタンの国民の多くは、カルザイ政権を自分たちを長年苦しめてきた軍閥の集まりとみなしその正当性を疑っている。同国の復興の遅れには新政府への信頼が十分でないことが少なからず影響している。ボスニアではムスリム系住民の帰還が進んでいないが、紛争時の指導者が罪を問われることなくそのまま居座り続けているためである。過去の犯罪の責任を明確化することによって社会の再統合は進展する。
過去の殺戮行為を不問にする恩赦はさらなる暴力を生み出しかねない。過去の暴力が許されるのならば、この次も暴力に訴えようと考える者が現れてもおかしくない。現にシエエラ・レオネやアンゴラ、コンゴ民主共和国では恩赦による和解が目指されたが、紛争は激化してゆく一方だった。武装闘争をすることの代償を払う必要がないとみなした反政府武装勢力は活動をエスカレートさせていったのだ。このように、戦争責任を不問とすることの代償は短期的にみても長期的にみても大変高くつくといえる。
われわれは今そこで起こっている暴力による重大な人権侵害を止めなければならない。恩赦が現在進行中の戦争犯罪を抑止するのには無力であることは過去のケースからも明らかだ。暴力による不正義を正すには正義を追求することが必要である。一国内において司法制度の存在が犯罪を抑制するように、国際的にも正義を追求することによって重大な人権侵害を押しとどめることができるだろう。
近年の戦争責任を明確化する動きは、人々の和平に対する態度に大きな変化を生じさせつつある。1980年代以降、民衆は正義のある和平を求めるようになってきている。戦争責任を不問にした上での和平合意は社会の再統合を阻みかねず、せっかくの和平合意が台無しになることもありうる。正義なき平和よりも正義のある平和の方が長続きすることは多くの地域で確認されている。
最後に、和平の実現と正義の追求(訴追)の順序についても触れておきたい。多くの人は訴追よりも先に和平を実現すべきだと考えているが、その点について異論はない。ただし、大量殺戮をはじめとする重大な人権侵害があったのなら、それは近い将来必ず訴追されるべきである。暴力行為には必ず罰が伴うことが明確にされれば、それが紛争再発を抑止する一要因となりうるだろう。
以上のように、紛争時に残虐行為を犯した指導者たちの責任を問うことは、和平の実現の妨げとはならない。むしろ紛争後の社会の長期的な安定を目指すのであれば、戦争犯罪者の責任を積極的に追及すべきである。正義の追求は和平の実現のための重要な手段として見直されなければならない。
|