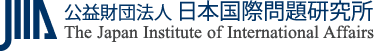|
「開発協力政策」をテーマとする第二セッションは、大野泉政策研究大学院大学教授の司会によって進行された。まず下村恭民法政大学名誉教授が「大震災後のアジア開発協力政策を考える」と題した基調講演において、震災によってアジアの開発協力にいかなる環境変化が生じたのか、またその新しい状況下でいかなる開発協力政策をとっていくべきかを検討した。下村氏は、①震災によって半世紀ぶりに被援助体験をした日本はこの経験を活かし、国際援助社会が援助される側の論理を十分に考慮し、「援助側と被援助側のコンセンサス」の原則を真に実行できるよう働きかけていくべきこと、②アジア域内に「共助」の芽が広がりつつある震災後の潮流を活かし、環境問題などのコモン・アジェンダにおける開発協力を通じて、紛争のアジアに信頼を醸成していくべきことを論じた。
ディスカッサントを担当した朽木昭文日本大学教授は、アジアの各地で産業クラスターが形成され、それがアジアの経済成長において重要な役割を担っている状況をまず理解すべきことを指摘した上で、東北経済の復興は、東北・北海道を一地域と捉えて産業クラスターを形成していく形で行わなければならないことを論じた。また、アジアで形成されている産業クラスター間のネットワークに日本が関与していくため、下村氏の提示した枠組みの中で開発協力政策を積極的に推進していくべきことを提起した。
湊直信外務省大臣官房ODA評価室長は、下村氏の①、②の論点について、今回の被援助国としての経験を踏まえ、具体的な援助とともに「メッセージ」を伝えることが、ドナーと被援助国の相互理解にとって重要であること、震災のような予測困難なリスクに対しアジア諸国が一致して解決に臨めるようなネットワークの構築を、アジアに「共助」の芽が生まれつつある今推進していくべきことなどを述べた。
質疑応答では、削減傾向にあるODAを再度増加させていくべきこと、そのためにはODAの成果を積極的にわかりやすく発信し、ODAに対する国民の支持を獲得していくべきことが議論されたほか、原発問題について、問題が発生したからといってこれを即座に放棄するのではなく、今回の経験を踏まえてイノベーションを図り、その経験を途上国等に向けて発信していくことでアジアおよび国際社会全体の平和に貢献していくべきではないかとの意見が出された。
最後に国際アジア共同体学会代表である進藤榮一筑波大学名誉教授が総括挨拶を行い、第一、第二セッションの一連の議論を踏まえ、震災後の現在が欧米の時代からアジアの時代へ、国家対国家の伝統的安全保障の時代から人間の安全保障の時代へ、競争と収奪の時代から共助の時代へと移り変わる大変動期にあることを強調し、シンポジウムを締めくくった。
|